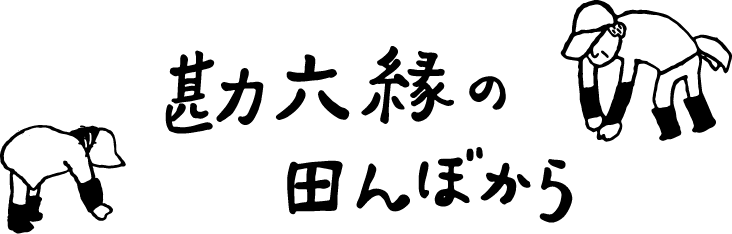6月9日までかかった田植え。心配をよそに、順調に穂を出しています。
こんにちは。陽佑です。お盆期間、いかがお過ごしでしょうか?
私たちにとって、4月の種まき準備から6月上旬までの田植え、それが終わったら除草作業を7月20日頃まで行い、7月20日からは畔などの草刈り、そしてようやく8月のお盆頃になると、緊張感のある日々から、ひと休みできる期間となります。久々の投稿ですが、作り手として、田んぼのことや自分の気持ちを整理してみます。
去年と一昨年は、ようやく米農家らしくなってきたかなと成長を嬉しく感じる春でしたが、今年の春は、やっぱりまだまだ未熟だなあ、と不安が大きい春を過ごしました。原因は大きく2つあり、ひとつは、苗づくりがうまくいかなかったこと、もうひとつは、ここまで雨が多い春は初めてで、作業は遅れ、トラクターを泥んこにしながら畔塗りや田起こしをしたことで、果たしてお米を無事に収穫できるだろうかと、心配になってしまいました。
苗づくりの初期に低温になったことで、発芽率が悪く、生育もまばらになってしまいました。低温はこれまでも経験しているので、そうなっても大丈夫なように準備をしていたつもりでしたが、どこかの準備が足りなかったようです。時間をかけて考えてみて、ある程度原因の予想はついてきました。
作業の遅れは、結果として田植えが6月9日までかかりました。ここまで遅い田植えは初めての経験でした。これまでの経験上、私たちのような寒冷地での田植え期間はある程度限定されており、ここまでかかってしまうと、あまりよくないのではと考えていました。また、ここまですべての田んぼが乾いていない状態で田起こしなどの作業をしたことも初めてで、果たして、田んぼになるのか、ということが分からない状態で作業をしていました。
田植えが終わり、田んぼの水管理をしながら除草作業をする期間に入ると、苗の姿を見ながら、
「大きくなった。元気そう」
と感じるようになりました。特に、朝と夕方は時間をかけて水管理(田の見回り)をするので、ぐんぐん大きくなっていく苗の姿には、励まされました。これならちゃんと収穫できるかもしれないと希望を持つようになり、苗は頑張って生きているので、自分もあきらめることなく、出来ることを精一杯やろうと、自分の気持ちも変化していきました。
そして、いまの田んぼの様子をみると、穂が出始める日にちは例年通りでしたが、出揃う日にちは早くなりそうです。こんなに色々あった年なのに、という感じなのですが、私が思っている以上に、稲たちは強いのだと思います。
もちろん、秋に収穫が終わってみないと結果が分からないのですが、今のところ、春の不安が嘘のように、元気に育っています。

お墓参りのあと、お墓近くの田んぼを見る。アブ除けになる「おにやんま」と共に。
元気に育っている要因はいくつかあると思いますが、一番の要因は、田植えが遅くなったこと、なのかなと考えています。私たちの主力品種は、ササニシキ、遠野4号、亀の尾、の3品種です。どれも早生(わせ)品種にあたりますが、遠野4号は、早生の中でもさらに穂が出るのか早い特徴があります。そのため、遠野4号は寒冷地向きであり、3年前までは収穫量が安定していました。
でも、去年と一昨年は遠野4号の収穫量が悪く、もしかすると、品種の構成を考えなおさないといけないのかもしれないと感じていました。そんな中、田植えが遅れてしまったことで、偶然にも遠野4号の生育もよいです。災い転じて福となす、になるかもしれません。
さらに、私たちがずっと悩んでいたクログワイという草対策も、田植えを遅くすることで、ある程度の効果が得られるかもしれません。クログワイは、私たちの地域では6月初旬に発芽します。そのため、発芽してから代かきをすることで、一度クログワイを抑えてから田植えができたので、今年はクログワイが少ないのではと考えています。
春の不安が嘘のように、いまは大きな期待を持ちながら、秋の収穫を待っています。繰り返しになりますが、収穫して結果が出てみないことには、最終的に何が良かったのか、何が課題なのか、分からないです。もしかすると、いまの期待が見当違いだった、ということもあり得ます。
9月下旬から始まる稲刈りまで、あとは水管理をすることがお米づくりの中心です。それと、穂が垂れ始めると、いっきに鹿が食べにくるので、電気牧柵の管理が一番大切な仕事です。お盆期間中はひと休みしてしますが、収穫が終わるまで気を抜かないようにしていきます。
久しぶりのブログ、文字ばっかりになってしまいましたが、ご覧いただき、ありがとうございました。