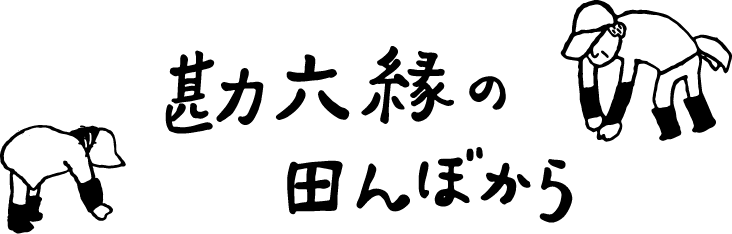土用のパワー。
こんにちは。
本日の担当は裕美(嫁)です。
ばっちゃんたちとの草とりを無事に終えて、夏の土用に入りました。名残惜しさを、私たちも、おそらくばっちゃんたちも感じつつ。

草とり最終日の背中。アブリパークでした(アブだらけの田んぼ)。
「土用に入ったら、田んぼには入らないもんだじぇ」という、じっちゃんばっちゃんたちの言い伝えのもと、7月19日をもって、除草作業は終わりとなりました。完了ではありません。おしまいです。草がなくなったわけではけしてありません。草に負けないくらいに稲が元気でいられるよう、入れるくらい除草機で入り続け、ここは外せないという田んぼは手でも取りました。
今年は、春に雨が多く、乾いた状態で田起こしできなかったことがどう影響したか、まだ未知数であります。正直なところ、不安要素でしたが、田んぼの土はやわらかく、手取り除草していても草が抜きやすかった。稲の根にとってもよい影響だったように感じています。冬~春に土がよく乾いたことがよかったかも。
ここ数年、「手で草を取らなくてもよいくらい、稲が元気でいる」状態というのを、目指しています。「手で草を取れる人を育てる」ということに、かなりの難しさを感じたし、現実的ではないというのが、さびしく、不甲斐ないのですが、我々には厳しいところでした。そこで助けられたのが、深水管理という考え方。自然栽培の先輩農家さんから教わりました。

水を抜くときのブラックホール感。ものすっごい勢いで水が流れていきます。つい、深水こわいとつぶやきました。
詳しくは陽佑から伝えたいと思いますが、深水管理は独特すぎて、私は「???」なところが多かった。自然栽培は稲がいかに分げつして、穂をつけられるか。そのためには、深くなりすぎないように水管理して、分げつを。と思っていました。が、一昨年から生育調査をしてきて、そうではないことがわかりました。なんと、過剰分げつだったのです。自然栽培で、この土地で。衝撃でした。
過剰分げつというのは、稲が穂をつけたいと思える数以上に、どんどん茎を増やして、茎の数の割に穂が少ないというかんじ。穂を出す前に稲が疲れちゃうイメージがあります。しかも、浅水で管理すると、草にとっても嬉しい状況に。草と稲のどちらが勝つか負けるかの戦いになってしまいます。
深水管理することで、過剰分げつを抑え、草も抑えられる。そのために丈夫な高い畔づくりが重要です。理想の畔づくりは一年やそこらでは難しく、何年かかけてどんどん丈夫に、高くしていきます。

がしがし削って、ぺたぺたかためていきます。

ぺっかぺかの畔のできあがり。かったい。
昨年は、途中まで深水管理でうまく草を抑えていたのですが、いつから中干しするのか問題が難儀で、タイミングを誤ってコナギが旺盛になってしまった田んぼがありました。今年は、稲と草の状況、その田んぼの秋の乾きやすさ(収穫作業時に大切なこと)を見ながら、それぞれの田んぼに合わせたタイミングで中干ししています。
一見、大丈夫!?と不安になるようなやり方なので(いまだに私も慣れない)、出穂の様子を見てみないことには、稲にとって本当によいことだったのかというのは判断しかねます。またご報告したいと思います。
土用に入ったら、稲だけでなく野菜も、ぐぐっと大きくなったように感じます。土と太陽のパワーがすごい。夏ってのは8月だと思ってきましたが、7月なのですね。昔のこよみやじっちゃんばっちゃんたちの言葉には、かならず理由があり、根拠がある。昨今の天候の変化と照らし合わせて、今、この土地にどう生かすかは、我々次第と思います。
さいごに。暑い日はやっぱり川へGO。

里江さんちの目の前の川。毎年夏はここへ。最高。
暑い日が続いて心身おつかれかと思います。ゆっくりお風呂に浸かって、ゆったり過ごせる夜でありますように。ありがとうございました。
【勘六縁のお米】
*令和6年産のお米は完売いたしました。ごめんなさい。
*新米予約は9/10からの予定です。
*勘六縁のいろいろはホームページからどうぞ。